肋骨を高く引き上げ、横隔膜を下げる。これは呼吸の入る容れ物を拡げるということです。
この広がる方向性を維持して呼吸をするというのは四つ這い動物の時代から持っている呼吸のシステムであり、立って生活を営むようになった人間もその基本を変えず呼吸をしています。
ゴム風船の上部に貼りついた傘の骨を開くように肋骨を拡げ、風船の下部にある横隔膜をピンと張るように押し下げる。蝿帳をタテに引き延ばして、傘の骨がずっと下の方まで伸び、下端には横隔膜が張られている。 それとも、ジンベイザメが大きな口を開けて泳ぐと広がった空間に水がイケイケに通る等々、感じ方は人それぞれですが、胸腔や喉を拡げる力のかかり方のイメージが持てないでしょうか。下端も広がろうとしているから、「肋骨が横隔膜を引っ張り拡げる働き」と「横隔膜の収縮」とが拮抗している。

肋骨と横隔膜とで容れ物が広がり、中の空気は外とイケイケで、その容れ物の広がりを失わず息が出入りする。 ただ吐くのではなく、息を吸い入れる働きの横隔膜を吐くときにも働かせ、空間を小さくする働きに対して空間を広げ、吐く働きに対して抑制的に働いて空気量をコントロールする。それらの働きは腹圧が上がるとか、広がる働きが喉周りでも生じて声帯の伸展を生み出すなどの一連の連携の結果も生み出している。
このコントロールは心の動きを支配したり良い声を出そうとするときに不可欠な働きだが、起きて活動している間は常に、時には強く時にはデリケートに働くことで望ましい生命活動が行われる。
吸う働きと吐く働き、上げる働きと下げる働き、伸びる働きと縮む働き、などなど反対の働きが同居することでより良い横隔膜のコントロールが可能になり、腹圧が高まり、血行が良くなり、自律神経のバランスが取れ、脳波が調い、心が豊かに安らいだ状態になることができる。しかし現実にはこの反対に、肋骨を萎ませてコントロールしにくい状態で使っている人が多い。それも歳をとるほどにその度合いが強くなる。何とも“もったいない”ことだが、日々同じ使い方をすることによって、すなわち、毎日毎日萎む練習を積むことによって、歳とともに萎む。萎むという以外にも多くのことで、本来生命が私たちに用意している機能を生かさず、結果として生命の嫌がることを心身に強い、そのために喜びを減らし、病や短命を引き起こしてしまう。
萎まない生き方
いくら好きなことをして楽をして生きていると思っていても、「それは気のせい」ということが多い。行動の元になる意識の認識のところで、誤解をしたり感受性が狂ったり、その行動が結果的に自分の生命を喜ばせていないとしたらどうだろう。楽と思っていることが本当は楽ではなく、身体や心を痛めつけているとしたらどうだろう。本来の自分、生命の求めている方向とずれが生じて、気が付いた時には目指すところと遠く離れているとしたらどうだろう。誰もがいい人生を歩みたいと願うのに、多くの人が得たくない病を得て苦しみ、思いと現実とのギャップに苦しむそのパラドックスを解決しなければならない。それを解決できなければ、何度チャレンジしても結果は変わらない。金や地位を得たとしても、時間や余裕を持つことが出来ても同じことだ。そして歳を取っても解決できないときには「歳だから当たり前、仕方ない」と自分に言い聞かせることになる。
呼吸が浅くなり体感空間が萎めば、喜びを生み出す“意識”も萎む。歳をとれば体の多くの機能が低下する。しかし、心の広がりや豊かさを得る力は心の働きだから歳とともに意識的に強化できる働きだ。しかしそれには呼吸の働きの協力も必要だ。そこで、自分を観察しながら、少しずつでもヨガが説く生活法をしていくことが必要だけれど、まずは、それが必要と思うためのきっかけになる最初の理解が必要だ。すべては自業自得であり、自分が自分の人生の創り主であり、今あるように自分を養ってきている。何が起ころうと人のせいではない、毎日の生活と心が創り出している自分なのだ。それなら真に豊かな生き方をするためにはどうすればいいのか。仕事、家庭、生活、それらの基準になる尺度を、大切にすることの優先順位を、生命の側から見直してみる必要がある。
さて、四つ足時代には楽に深い呼吸をしていた私たちは現在二本の足で立って生活している。立つことで別の呼吸のシステムを手に入れたわけではない。その呼吸の状態を維持するための背骨を軸とする全身の使い方を手に入れ、四つ足時代のままの深い呼吸ができるように変化(進化)している。その機能を十分に活かし生命を謳歌している人も多くいるし、若者にはその割合が多い。でも年寄りだけでなく若者であっても萎んでいる人が多くいるのも事実です。
なぜ萎んではいけないのか、そんなことを考えなくても生きていけるのに、と考えますか?
私たちは広い体感空間を維持していなければならない。それが心を調えるための必須の条件だからです。容れ物が萎むと心が狭くなり状態が狂ってきます。誰もが求めてやまない、“気持ちよく生きる”ということと体感空間の在り方とは歯車が噛んで動くように連動しているからです。
休んだり眠ったりしているときには多くの筋肉が休み、それに伴い肋骨を拡げている筋肉も休み、胸腔が萎みます。そして活動状態になるときにはその容れ物を拡げ、いつでも酸素をたくさん取り入れることができるようなバージョンにシフトされます。それは、背スジに力がこもり、一つひとつの背骨についているそれぞれの肋骨を引き上げる働きが高まり、胸腔が広がり、より深い呼吸が可能になるということです。肋骨が引きあがって広がると、筋肉の起始が肋骨についている横隔膜が引っ張られることで反射的に、吸う息とともに力がこもり、結果として横隔膜は下がります。そうして胸郭が広がり呼吸をたくさん入れることのできる容れ物が生まれます。そして、広がったまま息を吐くために、肛門や骨盤底筋、体幹の筋肉などが働き、腹圧が高まり、心臓の負担を軽くしながら血行を促している。これらの私たちが生まれながらに持っている連動した本来の働きが、「活動する」または「活動しようとする」ことで全身が連携し始めるのです。この働きが生命の生み出す体感空間の広がりを生む働きと同じ一連のものだということです。意識という切り口でみればそれが心の広がりでもあるのです。
あれもこれも連動して生じているけれど、もし背スジに正しく力がこもらないとどうなるでしょう。それは生命の指令であるにもかかわらず、今話した多くの働きの連携が始まりません。当然自律神経のバランスが崩れやすくなり、危険にさらされたときには逃げることも身を守ることもできなくなるかもしれません。そこで、生命はただすごすごとあきらめるでしょうか、いえいえ、それは生命にとって致命的な問題だから、そんな状態を作らないでほしいと声を上げます。そこで生命の声を聴くことのできる人なら、ああ、私が悪うございました、背骨を緩ませているのがいけないのですね、すぐに何とかします。と、問題は割合簡単に解決に向かうでしょう。しかし生命の声を聴かないまたは聞こえない人の場合は厄介です。生命はどうしてもそのことを本人に伝えなくてはならないので、神経回路や分泌物質を使って、その危機を気分の悪さで伝え、何とかしろ~と叫んでいるのです。
本人が本人に伝えるというややこしい関係ですが、「生命の働き」が一番の主体として存在し、その指令を受けた「生命」が「心や身体」を道具として使って、生命の求めるところを実現しているということです。寝転んで休んでいるときなら何の問題もない背骨の緩みですが、活動時に背骨が緩み身体が萎んでいるということは生命にとっては由々しき問題だからこそ、それを気分で教えています。要は休息バージョンで活動することが無理だということです。
身体が重いとか気分が悪いとか、生命は色々な方法で伝えまた要求してきますが、間違った姿勢が身についているとなかなか呼吸の広がりを生み出したり維持したりができません。そのため気分の悪さや重さを解消できず、その気分が毎日の、一瞬一瞬の心のベースになってしまいます。そうです、気分は心のベース、気分が良ければ少々のことでは腹を立てないでしょう。心が心をコントロールすることができるまで心を進化させた人なら、体の痛み苦しみそして気分に支配されないかもしれません。でもほとんどの人にとって、まずは気分がよくなって初めて物事をありのままに見ることができ、そこで初めて自身の価値観から解放され、心が自分の都合から自由になり、清々しい心になることができます。気分が良いというベースの上で自分の心を見つめ、意図してこそ広い心や自由度の高い心が得られます。
そのためには、ただ背骨を立てればいいというものではなく、広がりを生み出しながら背骨を立て、そのまま気持ちの良い呼吸をする必要があります。何としてもこの働きを取り戻すことが必要です。体の健康、心の健康、健康的な良い声、気持ちよい人生、それらを取り戻すことを第一義に考え、それが自分だけの問題で済まないなら他の人や社会を巻き込んででも、その方法を生み出さなければなりません。
その方法を見つけた人が色々な伝え方をしてきていますが、それらはメジャーにはならず、反対にガセネタが世にあふれ、現代の迷信になっている筋トレのブームもその真実に近づくどころか、大きな間違いを世に流しています。
たしかに、身体の使い方は筋肉の使い方と言えなくはありませんが、○○筋を伸ばすとか鍛えるというとらえ方はどちらかといえば持たない方が正解です。もちろん、治療のために行われる場合は別ですし、スポーツ選手はそのトレーニングだけをするわけではないので、副次的に働きにくい筋肉を強化するという考え方が役に立つことでしょう。しかし、一般の人が健康のためにと○○筋をトレーニングするのは問題です。
身体の使い方―方向性
身体を動かすときの筋肉の働き方を見たとき、それぞれの筋肉が単独で働いているでしょうか?
私たちが動作をするとき、そこには動く方向と力(ベクトル)、そして速さ(スピード)や間(タイミング)があります。その時に一つの筋肉に意識を向けて動かすでしょうか。いや、私たちは決してそんなことをして生きてはいません。多くの筋肉が助け合いながら、ある時には拮抗し合いながら、方向やスピードを生み出しているのであって。決して単独の筋肉の働きで体を動かすことはありません。私たちが感じているまたは意識しているのは方向性と力加減ですが、トレーニングしようとして間違えやすいところがこの方向性です。
どこかを一つの方向に向けて動かすためには多くの筋肉の協力が必要です。呼吸をするために胸郭を開くといってもどのような方向に働くかが大切です。上げるべき気を上げ、下げるべき気を下げる。これを間違うと呼吸が萎みます。
息を吐くということ一つをとってみても、ため息をつくときのように肋骨を下げる方向に使うのか、それともうれしくて喜んで伸びやかに声を上げているときのように胸骨の先端(天突)が引きあがるような吐き方をしているのか。息の入ってくるときには横隔膜が働きますが、その時に胸郭が一緒になって下に向かうのか、それとも拮抗して上向きに働くのか、それが方向性の問題であり、自分の身についた方向性に沿って心の方向性や傾向を生みだし、またそれがお腹や首の使い方を支配し、同時に呼吸の深さや自律神経の働き方を規定しているのです。ですから、方向性を持った身体の使い方を自分に課し、毎日毎日それを自分に教え養ってこそ呼吸法といえるし、筋肉も結果的に正しく養われます。
方向性を間違えてトレーニングすればそれは自身の心の方向性を生命の喜びから遠ざけ、己を貶める結果になります。ただ吐いてもそれは呼吸法ではないし、ただ筋肉を使ってもそれは本来の体操法とは言えません。ましてやヨガとはかけ離れたものでしかありません。
次の記事
→ 世の中の当たり前

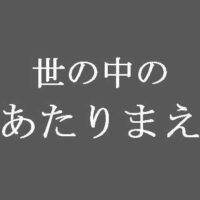
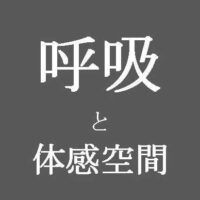
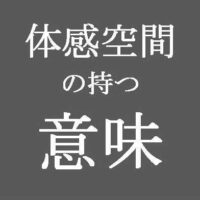
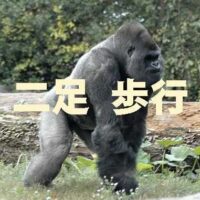
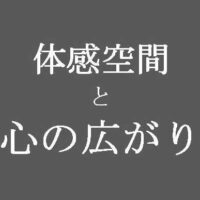
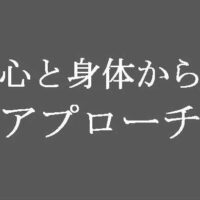


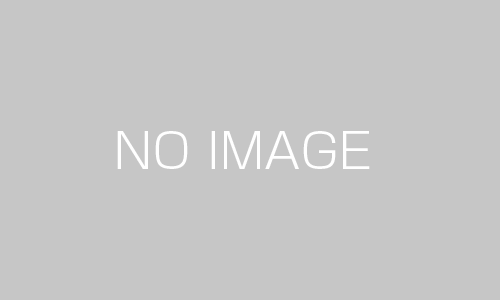
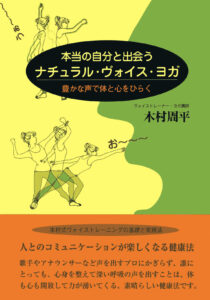
この記事へのコメントはありません。