前回は四つ足動物たちと私たち人間との呼吸について考えてみました。
這うか立つかの重力のかかり方の違いで体の使い方が大きく変わり、そこで、筋肉の使い方や呼吸の仕方も当然 変わってきたことでしょう。しかしその実、私たちは哺乳類の範疇を出ず、根本のところでは、四つ足の動物たちと変わらない「同じ器官」を使い「同じような呼吸」をしているということでした。
四つ足たちの背骨は重力に対して直角に置いた梁のような形で、内臓や肋骨をそれぞれの位置でぶら下げるようになっています。ですから、私たち人間のように、肋骨がお腹の方に下がったり、内臓がお尻のほうに落ちて押しやられたりというようなことが起こりえない構造になっています。そこで、同じような器官を持ちながら立って生活する人間は、立っても彼らと同じように本来の呼吸の機能が失われないための別な働きを進化させてその呼吸状態を維持していたと考えられます。
その呼吸を維持して正しく生きていたからこそ、人類は数を増やし、今のように発展した社会をつくことができたのでしょうが、文化の発達とともに失っていった働きが限界を超えたことで、人間の生命に根付いた生活や社会が崩壊に向かっていこうとしているのではないでしょうか、
四つ這いから起き上がって立つ生活になるにつけ、肋骨が下がらないように背骨が支え、内臓が下がらないように背中やお腹の筋肉を駆使して、本来の正しい呼吸を維持しながら立って行動するということを学び覚え、そして発達させてきたにちがいありません。野生のゴリラや、現代ではほとんどいなくなった原始生活者たちが生活するさまを撮影した映像を見ることが時々ありますが、見る度にこのことを確信します。
私たちの生命は生命自身を最高に生かすことができるようにしながら肉体を変化させてきています。今お話しした四つ足たちが持っているような深い呼吸の能力、そして全身に血液をくまなく流すような身体の使い方など、立ちながらもその能力を獲得し発達させながら生活をするようになった人間のはずですが、どうしたことでしょう、どこでどう間違えたのか、私たち人間の多くが肋骨を下げ内臓を下垂させて暮らしています。
立つことによって力のかかり方の変わった呼吸器官を、四つ足時代と同じように働かせるための能力は四つ足時代には必要のなかった能力です。梁にぶら下がっているときの肋骨は重力に逆らわないでも、袋状の肺を開いておくための枠組み(肋骨)が背骨に対して直角に下がっているため、下がっているだけで広がりが生まれます。その広がった状態が当たり前であって、先月号の“犬が後ろ足で立ったときの写真”が教えてくれているように、彼らは後ろ足で立った時も、それはほんの一瞬のことかもしれませんが、それでもその時に肋骨が下がって萎むような使い方をしません。長時間の維持はできないとしても、それはあり得ないことなのでしょう、私たちのようにすぐに肋骨が萎むようなことはきっと生じないのです。
これらの気づきから、自分でもしょっちゅう四つ這いになり、猫のポーズや犬のポーズのような形をとりながら呼吸をしたり声を出したりしていてもう一つ気づきがありました。それは、私たちでも背骨を梁のように使い、背中や腰の不要な力を抜く、すなわち本来立つためには使わないでもよい筋肉を緩めておくことができれば、とても横隔膜が使いやすくなるということです。これは、現代の人間の多くが、本来使わないはずの筋肉を使って立ち、また姿勢を維持しているということです。腰痛も肩こりもこのあたりに一番の原因がありそうです。
横隔膜
猫やライオンの真似をして四つ這いになると、腰の筋肉を解放しやすく、横隔膜の前はもちろん、後ろ側も目いっぱい全面的に働かせることが容易になりますが、この話には少し解説が必要です。
横隔膜は大きな一枚の筋肉のように見えますが、実は多くの方向に働く筋肉群なので多くの起始部を持っています。胸骨、肋骨、腰椎、そして肋骨を支えるすべての胸椎も同じ働きに直接関わっています。ですからどのような姿勢をとっていても横隔膜を働かせることができる反面、背骨の使い方ひとつで制約も生じてしまいます。それは、姿勢を間違うことで足腰背骨をうまく使えず、そのために横隔膜を十分に使うことができなくなっている人がとても多いということです。
どういうことかというと、立ち姿勢で体の重心が重力のかかる線上にあれば問題ないのですが、これが外れることで、不要な筋肉の緊張を余儀なくされるのです。直立静止している姿勢で考えるとよくわかると思いますが、足裏の重心点から垂直な線を立て、その線上に背骨を積んでいき、その重力のかかる線の上に体の重心が乗れば背骨を起こしておくための力は不要です。動いている身体であっても、この状態が基本にあれば身体を楽に動かすことができます。ところが、背骨が重力線の上になければ倒れようとする背骨を起こしておく力が必要です。姿勢が悪く、重心線がいつも外れているとしたら、それを起こしておくための筋肉は常に緊張を強いられて疲れてしまいます。しかし疲れたからといってその力を抜いてしまえば背骨を起こしておくことができないため、その筋肉はいつも硬直して背骨が倒れないようにしているのです。この姿勢はとても疲れますし、また常に緊張を強いるので、心の緊張まで引き起こしてしまいます。そしてもう一つの大きな弊害は横隔膜の使い方に影響するということです。
その弊害とは、本来は解放されていて必要な時だけ力を発揮すべき多くの筋肉が、姿勢維持のために使われているために、胸や腰の筋肉を自由に使えなくなり、それが肋骨と横隔膜の拮抗に影響し、また多くの筋肉の集合である横隔膜の一部しか使えないということを引き起こすのです。背骨を起こすために不要に腰や背中を緊張させていることで横隔膜が自由に動けないということです。
肋骨の動きはある程度目に見えるのでわかりやすいですが、横隔膜の動きは見えにくく簡単にはわかりません、しかし、猫のような動きをしながら呼吸のいろいろなパターンを 観察してみると、背骨を梁のように使うことで、横隔膜を自由に働かしやすくなるということがわかります。
横隔膜の前部と側部は、肋骨が下がっていてもある程度働かすことができますが、肋骨が高く引きあがっていて初めて、デリケートにも強くもより自由に使うことができます。また、後側は前側に比べてずっと使いにくいのですが、それは、後側の起始は腰椎の下部についているため、腰の使い方と密接に関係していて、腰がうまく使えないと後ろ側が働きにくいからです。身体が健全であるほど横隔膜を含めた呼吸器全体もうまく働きますが、横隔膜をフルにうまく使えている人は少ないですし、私の見る限りでは特に日本人には不得手な人が多いように思います。世界中の人を見ての話ではありませんが、歌声、話し声、映画の声など、多くの人の声を聴いた範囲でそう感じます。
このことは、背骨を立てておくための筋肉が弱体化することで生じていると考えられます。そのため、本来はもっとデリケートな仕事のための筋肉や、屈んだ姿勢を維持したり重い物を持って支えたり引き上げたりするための筋肉、それらを使って背骨を立てるという動作をさせている人が多く、本来の役目ではない仕事をさせているためにそれらの筋肉が硬化してしまい、横隔膜をデリケートに使うという作業に対応できない腰の状態になっていると考えられます。
腰痛は人間の宿命ではない
腰痛が生じるのは立って生活するようになった人間の宿命であると言う人が多いですが、その考えは誤りだと思います。生命はそのあたりのことをすべて完全に把握して人間の身体をつくっているはずですが、人間がその使い方を誤ったために生じていると考えるべきです。それは、生命が間違いを犯すものとして人間を存在させていることが間違いであると考えるか、それとも、時間経過とともにその間違いも修正していく存在として生命があると考えるかの違いであろうとおもいますが、後者が正解であろうと私は考えます。どのように考えようとも姿勢の誤りは腰痛どころか、呼吸を阻害し、血流を悪くし、自律神経の働きのバランスを壊し、ひいては免疫力の異常や低下まで引き起こしています。これらのことはいくら筋肉の勉強をしてもわかるものではなく、どんなに頭のいい人であっても使うべき筋肉と解放しておくべき筋肉を頭で学ぶことはできません、地球に暮らすすべての人にとって、自分の身体で体得するしかないのです。
さて今回もほとんど呼吸の話、ここでやっと母音メソッドの話に移りますが、今回の話で四つ這いのネコのように腰の力を抜いておヘソが下がったところから上体を起こしてくるとどんな姿勢になっているでしょうか。実際に試してみましょう。
当然多くの筋肉が働くことで起き上がれるのですが、身体の使い方の正しい人なら、肋骨が広がり肋骨と横隔膜の拮抗で胸郭が大きく広がり、呼吸の拮抗が強くなり呼吸が深くなっていることでしょう。もし、腰が反ってお腹が出た姿勢になるとしたら、それは背骨を起こすときに肋骨を共に引き上げる働きが足らなかったのです。背中を締める働きが足らないか、お腹を締める働きが足らないかで、胸郭が萎んでしまったのです。胸骨の先端の「天突」を高く、肩が下がって肩甲骨が締まるように起こしてくることができれば、肋骨が高く胸郭が広がり横隔膜も働きやすくなり、結果としてお腹が締まります。この状態から肛門を締めて声を出せば、横隔膜の前後左右が全面的に働くことで、体内に生じる体内空間がより円く広がり、どの母音の音も出しやすくなっていることでしょう。それはどの母音の働きも高まっているということであり、言葉を換えれば、あいまいな母音の働きが大きくなっているともいえるのです。身体が広がり呼吸が生み出す体感空間が満遍なく広がっていれば、喉や口がどのような母音を出そうとしたときにも対応できます。この事実から見れば、広がりが響きを生み、締まる働きが指向性や言葉を生み出していると考えられます。
健康・良い声・集中力・統一力、どこが目標であっても、呼吸の状態が変わり、充実感・安定感・楽さ・気持ちよさ・意識の深さなどを自分のものにしなければ実現できないことだと思いますし、また、ここからのアプローチが一番の早道ではないかと思います。
次の記事
→ 呼吸と体感空間

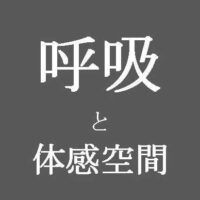
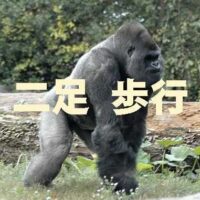


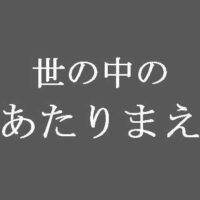
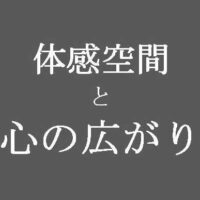
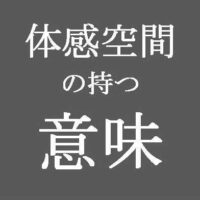


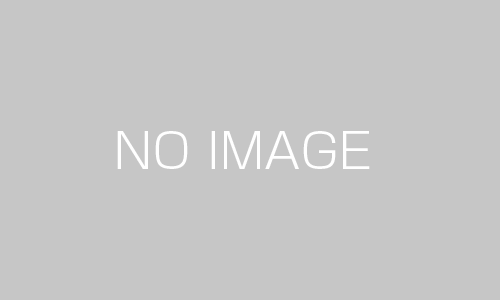
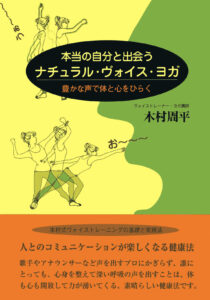
この記事へのコメントはありません。