呼吸の働き-拮抗と体感空間
呼吸法と呼ばれるものがあり、いわゆるヨガの行法の中にも多くのやり方が伝えられていますが、それらは何のためにやるのでしょう。もちろん酸素を多く取り入れるというような健康増進法ととらえることもできますが、本来のヨガの目的に思いを巡らせるなら、その目指すところは高く、《常に安定した深い呼吸のできる能力を養う》ということ、すなわち《呼吸コントロールの力を養う》というところにあります。ただ吸ったり吐いたりではなく、呼吸コントロールによって意識が広く深くなるような心身の使い方や生き方ができるようにすることに意味があるからです。
「意識が広く深く」というのは、心が広く身体がゆったりと和らいだ、「体感空間」の広い状態と言い換えることができます。そのような呼吸が健康度にも精神生活にも、また快く豊かな声がでるのにも一番大切なものです。この「体感空間」については後で詳しくお話をしますが、これは肋骨と横隔膜が創り出す精妙な意識であり、ここを求めて呼吸法を行うことで本来のヨガの求めるところに近づくことができます。
また、呼吸は意識的にも無意識的にもできるので、無意識の働きを意識的にコントロールする鍵にもなります。呼吸を意識的に深く保つことによって心の豊かさや自律神経の安定を保ち、また自分らしい良い声を育てることも出来るようになります。でも、ただスーハーと呼吸を長くしたり強くしたりしてもコントロール力が身につくわけではありません。まずは私たちの呼吸が本来どのように行われているのかを知って正しく取り組む必要があります。
呼吸のために使っている肋骨や横隔膜、その他多くの器官の働き方について長年研究をするうちに深い呼吸を手に入れるための「呼吸コントロールのメカニズム」についての体感とその意味についての気づきを得ることが出来ました。しかし、この気づきを説明できるような、体験に基づいた考察を読んだり聞いたりしたことがないので、それを体験体得するための実践方法とその意味について紹介しようと奮闘しているところです。そしてその一番のポイントは、正しい呼吸は拮抗する働きで成り立っているということです。
拮抗の働き
拮抗の働きは身体の中の色々なところで行われています。例えば、外的な刺激が変化したときに体内の状態を一定に保とうとするときなどには、血液の状態や自律神経の働きを拮抗という精度の高い方法でコントロールしています。
その恒常性を保つためのコントロールは、あらゆるところで色々なやり方がされますが、無くなったら足す、増え過ぎれば捨てるというタイプのコントロールでは誤差が多く、身体の状態の恒常性を保つというような精密なコントロールはできません。筋肉の働きでも同じで、行きすぎたらやめて反対を働かせるというような雑なコントロールだと、踊りどころかスムーズに歩くことさえできません。
別なやり方として、相反する働きを常在させておき、その働きの程度で拮抗度合いを変化させれば精密なコントロールが可能になります。これが拮抗によるコントロールで、呼吸も本来はこの方法で精密にコントロール出来るようになっていて、そのように身体は作られているのに、その機能を充分に活かして使っている人は僅かです。でも、一芸に秀でた達人といわれる人たちはその働きを使いこなしています。本来は誰もがそのような能力を発揮するための機能を与えられているのに、歌を忘れたカナリアのようにそんな使い方は出来ないと思い込んでいるようです。
さてその拮抗が呼吸の中でどのように使われているか、本来はどのような使われ方をしているはずなのか、それを「三つの拮抗」という考え方で説明します。
三つの拮抗
1. 肋骨と横隔膜の拮抗(息を吸う働き)
(「吸う働き」、息の入ってくることのできる空間を開き広げておく働き)
2. 横隔膜と肛門・骨盤底筋群の拮抗(腹圧を生む働き)
3.「吸う働き」 と 「吐く働き」の拮抗
これらの拮抗が働いてこそ本来の良い呼吸になります。 次の記事で詳しく説明しますが、この拮抗が無くても生きてはいけます、しかし神(自然)に与えられている生の質を高め、より活かすにはこの働きを是非取り戻すべきです。
呼吸をするには肺の容積を大きくしたり小さくしたりしますが、これがそう単純な働き方をしているわけではありません。
強く走ったり運動した直後の呼吸は多くの酸素の供給のために、胸郭そのものを大きく広げたり萎めたりの呼吸をすることもありますが、広く深い呼吸と意識を維持している平常時は、胸郭や胸腔が広がる働きを持ったまま息を吐くことができます。もちろん、胸腔の容積を減さなければ息を吐くことはできませんが、広がる(吸う)働きのあるまま、吐く働きが拮抗することで自在に吐いたり吸ったりの呼吸をコントロールすることができます。しかし、心が乱れているときや姿勢が緩んだり崩れたりしているときには拮抗した呼吸ができず、コントロールされた状態にはなりません。
意識の広がり=体感空間の広がり
(これについては「13.体感空間と心の広がり」の項で詳しい説明があります)
活動していても静かにしていても、気持ちがゆったりと大きいときには、背スジの伸びる働きで肋骨が高く拡がり、それに対して横隔膜が下がることで胸腔が拡がっています。そしてこの拡がりを生み出す拮抗の方向性が「体感空間」というイメージ空間を拡げています。《意識の広がり》は、この《「体感空間」の広がり》と同じ呼吸の働きによって生み出されています。反対に意気消沈したときには肋骨が下がり、胸腔が萎み、「体感空間」も萎んで小さくなっています。
バレエやフィギュアスケートの演技者たちが手を大きく動かして表現をしますが、その手がただ動いているだけのつまらない演技をする人と、より大きな空間にイメージを描き出す感動的な演技をする人がいます。後者は全身で自身の感じている「体感空間」を表現していますが、この空間は息を吐いても狭まりません。良い演技者は、胸郭を挙げる働きと横隔膜を下げる働きとで息の入ってくることのできるスペースを常に広げようとしており、その働きに対して息を吐くための別の筋肉群が働くという第3の拮抗によってコントロールしながら息を吐いているのです。このとき、吐くことを止めて息を開放すると、息は自ずと第1の拮抗によって広がろうとしている胸腔に流れ込んできます。これは、吐くときに肋骨を下げて萎ませていないからこそ生じる吸気です。この広がろうとする働きが体感空間を生む働きの原動力です。
この呼吸コントロールは歌手や楽器の演奏者、舞踏家たちの演奏・演技に明確に表れています。また、冥想、動禅、座禅瞑想、多くの武道や芸道、多くの宗教での修行、そして儀式や礼拝など、呼吸コントロールを必要とされるところでは、目立たなくてもこれが強く働いています。実生活でも、心や身体の使い方に無理がなく常に広く豊かな心で生きている人もこの働きを活かす能力を持っています。
この広がる方の吸う働きと吐く働きとが拮抗し合い、広がる働きを失わないまま声を出したり生活や仕事をする、ということが出来なければ、常に心を豊かな状態に維持することは出来ません。この広がりが失われたときに心が萎むからです。体感空間の広がりは心の豊かさと同じものです。
また、発声法の原点もここにあります。この呼吸コントロールがヨガでいうところのプラティヤハラのために絶対に必要な条件であり、このためにこそ、これを可能にするための身体の使い方を覚える、アサナやプラナヤマがあります。
当然のことですが、良い呼吸はこの三つの拮抗だけで完結しているわけではありません。全身の協力でこのための足場を生み出すことによってできている働きです。例えば、肋骨が高く広がるためには背スジが伸びることが必要。そして横隔膜がそれに対して拮抗して働くには足腰やお腹の協力が必要です。
この足場は、重力に逆らうように天に向かって伸び、地に向かって押し伸ばすという人間にとって当たり前の作業をすることですが、それは人間が重力に逆らって伸びるという進化をし、全ての活動を重力に逆らう働きと共に身につけてきているからこそ必要で決して外すことのできない重要な作業です。そしてこれも全身の協力によってなされることが重要なのは言うまでもありません。
これらの働きを統一し、一つのこととしてまとめる使い方を身に付けることが丹田(肚)で動作するということです。その上に声をよりよく響くようにするには、気道を広く保ったり、喉頭部や咽頭部を最適の位置に懸垂する必要があります。また、心が広く豊かな状態を維持するには、入ってくる刺激や情報をありのままに受け取ることができるための頭脳や心の力も必要です。これも人生をかけて手に入れるべき大事業ですが、身体や呼吸が広がるという豊かな気分と反対を向いていればどうしようもありません。
全てを通じて心身息を統一してこそ目的に向き合うことが出来ますが、このような沢山の個別の働きや、それらを統一して働くようにする大変なトレーニングをいったいどのようにすれば実現できるのでしょう。本来のヨガが掲げる目標が遠くかけ離れた世界に見えたとしても全く不思議ではありません。
たしかに、このような働きを個別に養ってそれを統合しようとするなら、それはとてつもなく難しい作業になることでしょう、しかし、それらの働きや機能は本来生まれながらに誰もが持っているものですから、その基になる原理に従って必要な働きを養うことで、後は生命がそれらをまとめて働くようにしてくれるという大きな救いがそこにあります。
ヨガの八段階や十段階と呼ばれるものはその原理の骨格を説くものであり、そこに到達するためのマップであり、進む方向も示されています。ここに書いた拮抗も原理に従って順を追ってやれば正しく身につけることができます。ただし、マップは全体を見てこそマップになります。それは人間丸ごと生きる全部でどの方向に進むのかというマップであって、部分のアサナやプラナヤマだけを取り出してもそれはヨガにはなりませんし、目標に向かうこともありません。でもその原理は簡単な言葉で表現できるし、なんだそんなことかと思うようなことかもしれません。しかし、その簡単そうなことが忘れられ、実践されることがほとんどないために、文明度が高く豊かそうに見える社会に暮らす人々の健康度は低く、殆どの人が病気になり、苦しんで死にます。精神的健康度も低く、自殺する人が多い。文明と共に戦争や殺人が減るならまだしも、人間心を養うことすら忘れられています。
人間には5千年も前から求めるところがあったからこそヨガが生まれ、現代に受け継がれているけれど、5千年もの間人間としての進化をせずにいるからこそ現代においても本来のヨガはかけがえのない大切なものなのです。
それでは、その原理の一つをお話しましょう。それは、
『どんな時にも、伸びやかに高らかに笑っているような呼吸をする』ということです。そして、『その高らかな笑いの呼吸を長~く引き延ばし、いつでもどんな状況でもその呼吸を維持する能力を身につける』ということです
なんだそんなことか、と思いますか? もし簡単そうに見えるならやってみることです。
なにもいつも大きな声で笑えということではなく、笑っているような呼吸の状態を維持すること、これこそが最初に述べた、三つの拮抗が有機的に結び着いて呼吸のコントロールをしている状態のことです。
ただ笑うだけではそれだけのものでしかありません。大切なのは、その『大らかな笑いと生活の全てを結びつける』ことです。ヨガをする人はここを求めてこそアサナやプラナヤマを自身の進化に貢献させることができます。生きることそのものの喜びを感じて生きるということをしないなら、いくらヨガらしいことをしてもそこには本質的な目標がなく、進むべき道が開いてくることはないでしょう。
深く豊かな呼吸を手に入れるには
それにはまず呼吸の拮抗についての考察を理解していただきたいと考えます。
胸に息を入れると横隔膜が上がり、お腹に息を入れると肋骨が下がる、という呼吸は上か下かどちらかに引っ張られていて拮抗しない力の使い方になっています。拮抗するとは反対向きのどちらにも同時に働くということです。しかしもしどちらかの働きが足らない状態だと拮抗させようがありません。まずは片方ずつでも、両方の働きを高めることが肝要です。
そこで私の提案ですが、まずは呼吸を変えるためのツールを手に入れ、そのツールを駆使していろいろなパターンの拮抗の働き方を身体に教え込みます。それができれば、あとは放っておいても身体が生命が拮抗した呼吸を始めてくれます。このツールが体感空間です。
ヨガという言葉
このサイトに出てくるヨガという言葉は教えたり習ったりすることのできる、様々なヨガではなく、自身の実践によってよりよい生き方を見つけていくための指針として提示されているヨガ、またはそれを実践することそのものを指す、本来のヨガを意味しています。
沖先生は、八段階目のサマーディの上にブッディ(仏性開発)、プラッサード(歓喜法悦)というヨガの十段階を説かれています。難しそうに聞こえますが、特別なことを言っているわけではありません。生きるということを追求することで生まれてきたものですから、誰にとっても身近なもののはずです。ヨガの用語は千年も二千年もの前の生活や当時の科学とともにあった言葉ですから、現代に生きる私たちは言葉そのままを鵜呑みにせず、一つ一つの言葉を自身の体験で翻訳し直す必要があります。自身の生命の声に従って生きること、そしてその声を訊くためにはヨガの説くマップを参考にして道を求める、他の人の解説ではなく自分の体験によって得た生命の声を指針として生きることよって、与えられた生命の喜びを享受して生きることができるようになる、というヨガです。
次の記事
→ 呼吸の拮抗
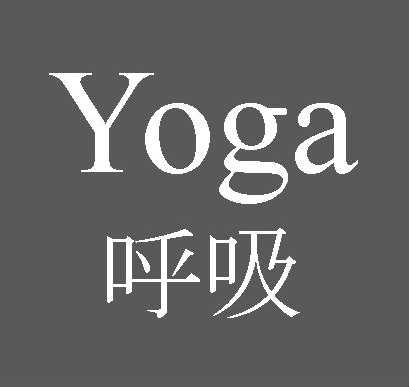
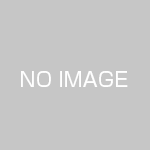

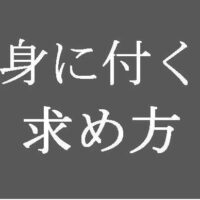
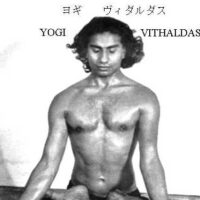



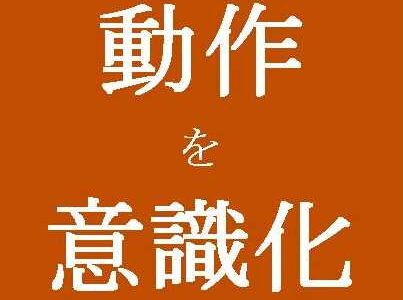
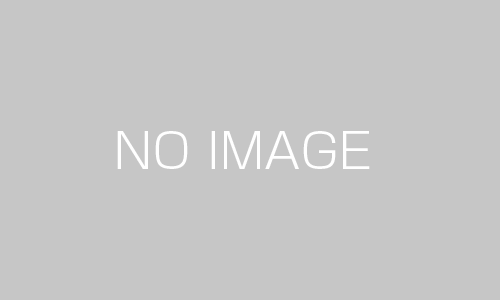
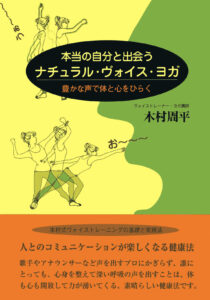
この記事へのコメントはありません。